(相殺の要件等) 【※ 本条解説へ移動する】
第505条第1項
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法 第三編 第一章 総則 条文一覧
以下、解説です。
【民法505条1項解説】
相殺とは、対立する債務を差し引きして対等額を無くすことです。
例えば、AがBに対して有する金銭債権200万円と、BがAに対して有する金銭債権100万円を差し引きし、BがAに対して有する金銭債権は帳消しになり、AがBに対して有する金銭債権が100万円となる、という場合です。
相殺の意思表示をした方の有する債権を『自働債権』、相殺される方の債権を『受働債権』と言います。相殺が可能である要件が揃っている状態のことを『相殺適状』と言います。
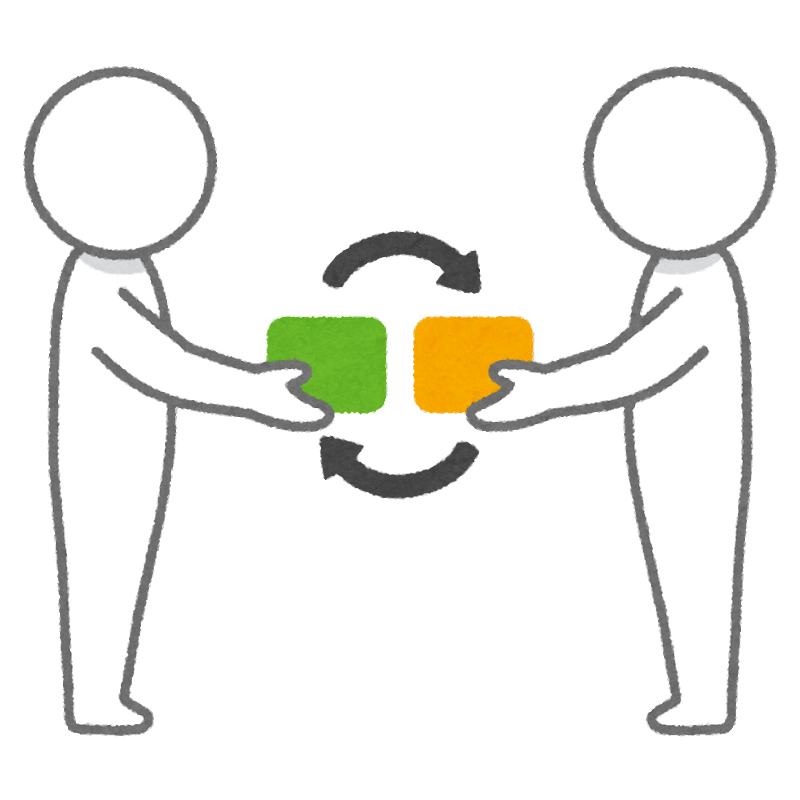 【相殺適状とは】
【相殺適状とは】
①双方の債務が対立していること
②双方の債務が同種の目的を有すること
③双方の債務が弁済期にあること
→自働債権が弁済期にあれば、受働債権は弁済期になくても相殺は可能です。自働債権の弁済期が到来していない内は、相手方(自働債権の債務者)に期限の利益(弁済期まで弁済しないでよいこと)があるため、勝手に相殺して相手方の期限の利益を放棄させることはできません。しかし、受働債権が弁済期になくても、自働債権を有する者は自己の期限の利益(受働債権の債務を弁済期まで弁済しないでよいこと)を放棄したうえで相殺することができます。
④双方の債務が有効であること
→消滅時効が成立した債権を自働債権として相殺する場合には、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合であれば相殺することができます(民法508条)。
⑤債務の性質が相殺を許すものであること
下記のような、法定で禁止されている債務や、当事者間に特約がある場合には相殺はできません。
・当事者に相殺を禁止し、又は制限する旨の特約があること、かつそのことについて第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったこと(民法505条2項)
→第三者の利益を害することがない場合には、当事者間の特約も可能です。
・受働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、または人の生命、身体の侵害による損害賠償の債務であること(民法509条)
→これを許してしまうと、受働債権を有している被害者の損害が救済されないというおそれや、弁済を受けられない債権者がわざと不法行為に及ぶおそれがあるため、禁止されています。
・自働債権が、受働債権の差押え後に取得された債権であること(差押え後に取得した債権が差押え前の原因により生じたものである場合は相殺可能)(民法511条1項、2項)
→相殺を認めてしまうと差押えの実効性が害される恐れがあるため禁止されています。
【相殺の方法】
当事者の一方から相手方に対して、相殺の意思表示をする(民法506条1項)。
【相殺の効果】
相殺適状になった時に遡って、相殺した双方の債務の対等額が消滅する(民法506条2項)。
2022年2月19日 ご執筆U様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)